
嵐を通販で買うなら
gacktの激安通販サイト
スゴ録の通販濃い情報
マルイの通販情報
ダウニーの激安通販サイト
パチンコの人気ランキング
夏帆の激安通販サイト
鋼の錬金術師の格安通販
アイドル 画像を通販で買うなら
花粉症の格安通販
gacktの激安通販サイト
スゴ録の通販濃い情報
マルイの通販情報
ダウニーの激安通販サイト
パチンコの人気ランキング
夏帆の激安通販サイト
鋼の錬金術師の格安通販
アイドル 画像を通販で買うなら
花粉症の格安通販
最終更新日:2009年10月14日
ハローワークの最新売れ筋情報
ハローワークに関する通販商品をご紹介しています。
|
地球のハローワーク 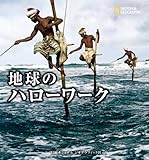 価格: 1,995円 レビュー評価:5.0 レビュー数:1 「地球のハローワーク」などと安易で腑抜けたタイトルでは ありますが、掲載されている写真は中々衝撃的なものが多く 人間の営みの凄絶さがうかがえる物も多々あります 特に貧富の差が激しい地域(中でも中国)の写真はどれも個性的で見ていて色々と 想像力が喚起されることでしょう 具体的には、中国の物乞いをさせられている赤ん坊は直球的な良さがあり、 南アフリカのコカコーラのペットボトルに詰められて売られている牛乳 といった一見地味ですが力強いメッセージが込められた写真も良いです 全体的に美しく芸術 |
裏のハローワーク―交渉・実践編  価格: 1,260円 レビュー評価:4.5 レビュー数:7 第一弾に続く続編だが、こちらもかわらず面白い。 一番印象に残ったのは、先物営業マンなどの儲け話を断る一番の方法は、 儲かるという旨を一筆書かせて書面に残すという方法である。 後々、裁判沙汰になることを考えるとたいていの営業マンは諦めるらしい。 なるほど! |
裏ハローワークスペシャル・セレクション―人に言えない仕事は、なぜか儲かる! (コスモ文庫)  価格: 510円 レビュー評価:4.5 レビュー数:4 世の中にはいろんな職業があって この本には 海千山千という言葉が似合う 奇妙な職業が満載です。 それが反面教師になって 普通の仕事をしている自分が誇らしくなります。 |
|
18歳のハローワーク 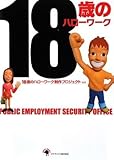 価格: 1,890円 レビュー評価:5.0 レビュー数:1 「資格で仕事する」、「自然の中で働く」など 現代を象徴するようなものも含まれていて、ズラリ300超。 前半部分の著名人インタビューも、読んでいて非常に気が引き締まる。 |
||
|
学校に行かなかった私たちのハローワーク  価格: 1,575円 レビュー評価:3.0 レビュー数:2 不登校には、人それぞれ様々な理由がある。なんであれ学校に行かないという理由だけで、子どもたちは社会の中で生きづらい思いを強いられるのである。「子どもの先行きや世間体を優先。今眼前に存在する我が子そのままでは許せない、愛せない親」。こんな残酷な話がまかり通って良いものか。 なんのための学校なのか?当然のように学校に行く、会社に行く。じゃぁどこかに帰属していない人は、人間の資格がないのだろうか。逆に国家が管理する学校のような組織の中で何も学ばなかった人は、生きている権利がないのだろうか。 残念ながら、現在社会の最大公約数的常識は、上の疑問に対して「是」と回答するだろう。 この本は少な |
33歳からのハローワーク アタシ探し シゴト探し 転職・再就職・起業・副収入  価格: 1,260円 レビュー評価:4.0 レビュー数:8 企画としてはすばらしいと思います。 20代後半に結婚した人ならそろそろ子供が幼稚園に行って 何かしよーかなと思うころ 独身でバリバリやってても、ワタシこれでいいの? とお悩みごろ。 そういう人たちがわんさかいそうな33歳。 目の付け所がいいです。 内容もなかなかいいです。 軽い文章ながら、なかなか冷静に現状を見ています。 また、紹介している職業ごとに現役の方にインタビューを しているので、実際になってみたときの自分をイメージしやすいです。 |
ボク達のハローワーク―萌え職業案内所 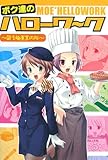 価格: 1,500円 レビュー評価:4.0 レビュー数:5 中身は様々な職業の紹介です。ただ飽くまでも萌えるような女性が書かれた女の子を見ながら色んな職業を概観出来るといういかにも萌えを狙っているハローワーク本です。女性しかなれないような職業が多いし、クリエイティブな仕事の紹介比率も高いです。普通の仕事は全く説明していない気がしました。これを読んで「よし就職しよう!」と意気込んでいる人には向きません。現実逃避のための就職本と考えましょう。 |
|
戦場のハローワーク  価格: 1,365円 レビュー評価:5.0 レビュー数:1 一気に読了した。いまハローワークというダサイ和製英語がブームのようだ。だが本書はそのブームなど軽く無視して、はるか日本人の未来の地点にいる。今の日本人の間違いなく必読の書である。さらに本書はかつてない中米ルポでもある。ラテン好きは是非! |
裏のハローワーク  価格: 1,260円 レビュー評価:4.0 レビュー数:31 いろんな仕事があります。 「金を返せないのならマグロ漁船に乗るか」なんて借金取りに言われそうで すが、本当にマグロ漁船に乗る事が出来るかどうか調べてみたいと思いませ んか。 裏の仕事と言われる様々な仕事を紹介しています。 事実と若干異なる表現も有りますが、仕事の中身を知るにはいいかもしれ ません。 夜逃げや、偽造クリエーター。大麻栽培、飛田新地で働く、本当に様々な 仕事を紹介しています。 世の中を知るには一度読んで見てください。 |
天職―発展途上国と向き合って暮らす  価格: 1,470円 レビュー評価:4.0 レビュー数:2 主な対象者を見た際は本書に目を通す気が半減したが(たとえ、主な対象者であっても限定し過ぎの感がある)、読み進めるうちに引き込まれていった。様々な過程を経て現在に至る人、国際協力の申し子のような人、皆様々な経緯でありながら、現在のそれぞれの今を確立していった様が窺える。国際協力について、途上国について、そして、自分自身の今後について、改めて向き合わせてくれた書である。就職活動をしている人たち以外でも、十分満喫できる要素があると思う。 |
Copyright (C) 2009 ハローワークの最新売れ筋情報 All Rights Reserved.


